- BizStyle ビズスタ東京版トップ

- Travel & Gourmetトラベル&グルメ

- あれから60年、まだまだ続く「ワインの旅」【ワイン航海日誌】

あれから60年、まだまだ続く「ワインの旅」【ワイン航海日誌】
![]() 2019年2月21日
2019年2月21日
私は、80歳を迎えた現在も、美味しい食べ物屋さんがあると聞けば200kmの距離があろうとも車を飛ばすことがしばしばです。旅は、その大小にかかわらず、私たちに心の豊かさや、感動、夢、人との出逢い、そして人間として生きる喜びを与えてくれますよね。
松尾芭蕉は人生そのものが旅だったと言っても過言ではないでしょう。『奥の細道』の冒頭には「月日は百代の過客」という有名なフレーズがありますが、過ぎ去る年もやってくる年もまた旅人であるという人生観には憧れます。私も昔、ある旅雑誌に「今日も旅人、明日も旅人」なんてタイトルのエッセイを書いた記憶がありますが、旅を愛した歌人は非常に多いですよね。
たとえば、かの西行は、こんな辞世の歌を遺しました。「願わくば花の下にてはる死なむその如月の望月の頃」。願いが叶うならば何とか桜の下で春に死にたいものだ、それも草木の萌え出ずる如月の満月の頃がいい。こんな歌を味わうと、花の吉野へ旅したいという気持ちがわいてくるのです。
というわけで、春四月、吉野(奈良県)の里を訪ねようかな、と。桜の下では、もちろんワインを愛でることになります。では、どの銘柄を選ぶのか…と今から悩みます。こうして、「人生の愉しみ」たる旅は、もう始まっているわけですね。

30代のはじめのことです。欧州にワインの銘醸地があると聞いた私は、前後も確かめずに旅に出ました。いま思うと、西行や芭蕉の気持ちに少しだけ触れるような経験だったのかもしれません。
ワインの生産地を訪ねる旅となれば、少々の危険は覚悟。当時は海外への渡航には制限があり、個人の観光旅行では500ドルまでしか持ち出すことができませんでした。為替の事情で異なりますが、私の場合は日本円で18万円くらいでしたでしょうか。それでも、目的がワインの旅なら、悩みなんかありません。何しろ、帰りの切符のことさえ考えていませんでしたから。
ちょうど半世紀前の1969年の春に私は旅に出ましたが、ワインの虜になったのは、そのさらに10年前のこと。南米チリのバルパライソの港町で、初めてワインを口唇に触れた瞬間のことは、今も忘れられません。あれから60年の歳月が流れ去りましたが、その間、ワインは一度たりとも私を裏切ったり騙したりすることはありませんでした。
私にとってのワインは、「IN VINO VERITAS」、真実はワインの中にのみ存在するという意味のラテン語の表現がピタリと当てはまります。「神は水を創り人はワインを造る」と語ったのは、『レ・ミゼラブル』の著者としてあまりにも有名なフランスの詩人・小説家、ヴィクトール・ユーゴ。ワインの周辺は名言の宝庫でもあります。
さて、前回のこのコーナーではワイン蔵の重要性をご紹介しましたが、今回は美味しいワインを作るための条件について書いてみます。
よいワインを造るには、よい葡萄が必要。その葡萄が育つためには、気候風土などの条件を満たした畑が必要となります。大地と葡萄、そして風土。人間の力を超える部分もありますので難しいのですが、日本にもワインのための葡萄づくりに適した土壌はあります。
そんな噂を聞きつけたら、旅心が黙ってはいません。というわけで、今回は北の大地、北海道は仁木・余市を訪れてみました。

小樽から函館本線で約30分、余市駅から仁木駅にかけての一帯は、現地ではフルーツ王国と呼ばれているそうです。りんごやさくらんぼ、葡萄造りの歴史は120年を超えており、特にワイン醸造用の葡萄は高いシェアを誇るとか。
フルーツ王国のはじまりは、いまから140年前の1879年11月に仁木竹吉ら360余名が徳島県から集団入植したことが契機となったようです。仁木町の名は、仁木竹吉にちなんでいるわけですね。今回は、この仁木町に2014年に作られた「北の楽園」仁木ヒルズを訪ねました。
このワイナリーが存在する仁木町旭台地区は、日照量、日照時間ともに十分で、地学的にはワイン用の葡萄が育つ条件を満たすどころか「恵まれすぎた大地」らしいです。ゼオライト(沸石類)やシーファーシュタイン(粘板岩)など混石土壌などにより成り立っており、仁木町ではミニトマトもこの気候風土の恩恵に浴しています。何と全国の6割を生産しているのだとか。

今回の旅は、実は今年の6月に大阪で開催予定の次期G20に関係があります。G20と時を同じくして、北海道倶知安町では観光大臣会議が開催される予定なのですが、これに先立ち参加各国の大使閣下をはじめ関係者が仁木ヒルズワイナリーに集まり、ランチを含む見学会が開催されました。私は、この光栄にもこの下見の会議に取材と解説役を兼ねてお招きいただくことができたのです。
仁木ヒルズワイナリーが誇るワイン蔵の見学後、眺望の良いダイニングルームで同ワイナリー自慢のウェルカムワインがサービスされました。ケルナー種100%で作られた「Hatsuyuki 2017」での乾杯。大使たちは当然、舌の肥えた方ばかりですので、僭越ながらワイナリーの土壌成分とともに詳しく説明させていただきました。
ワイナリー代表のワイン造りに対するパッションはテレビでも放映されていましたが、当日は、「Hatsuyuki 2017」に対して多くの大使閣下から絶賛の声をいただきました。色調の鮮やかさ、深みのあるアロマや酸と糖のバランスの素晴らしさ、料理とのコンビネーション・ペアリング(当日は、北海道産の素材をあしらった和魂洋才の創作料理が多数供されました)などなど。ルーマニアの大使閣下からは素晴らしいワインを一本いただき、アルゼンチンの大使閣下からは何度も繰り返しお気持ちのこもった握手をしていただけるなど、感動的なひとときとなりました。
Jamais homme noble ne hait le bon vin
崇高なる人間が良いワインを憎むことなど、断じてない(フランソワ・ラブレー)
私のワインの旅は、まだまだ続きそうです。
著者:熱田貴(あつたたかし)
経歴:昭和13年7月7日、千葉県佐原市に生まれる。外国にあこがれ(株)日之出汽船に勤務し、昭和38年まで客室乗務員として南米、北米を回りワインに出会う。39年にホテルニューオータニ料飲部に。44年~47年までフランス・ボルドー、ドイツ・ベルンカステル、オーストリア・ウィーン、イギリス・エジンバラにてワイナリー、スコッチウィスキー研修。48年ホテルニューオータニ料飲部に復職。平成3年に東京麹町にワインレストラン「東京グリンツィング」を開業。平成9年に日本ソムリエ協会会長に就任。「シュバリエ・ド・タストヴァン」「コマンドリー・デュ・ボンタン・ドゥ・メドック・エ・デ・グラーヴ」「ドイツワイン・ソムリエ名誉賞」など海外の名誉ある賞を数々受賞。その後も数々の賞を受賞し、平成18年に厚生労働省より「現代の名工」を受賞、平成22年度秋の褒賞で「黄綬褒章」を受賞。現在は一般社団法人日本ソムリエ協会名誉顧問、NIKI Hillsヴィレッジ監査役などを務めている。
★ワイン航海日誌バックナンバー
【1】もう1人いた「ワインの父」
【2】マイグラスを持って原産地に出かけよう
【3】初めてワインに遭遇した頃の想い出
【4】冬の楽しみ・グリューワインをご存知ですか?
【5】仁木ヒルズワイナリーを訪ねる
【6】酒の愉しみを詠んだ歌人の歩みを真似てみる。
【7】シャンパーニュ地方への旅
【8】エルミタージュの魔術師との出逢い
【9】ワインと光
【10】ワインから生まれた名言たち
【11】ワイン閣下との上手な付き合い方
【12】学問的・科学的とは言えない、でも楽しいワインの知識
【13】ホイリゲでプロースト!旅の途中・グリンツィング村の想い出
【14】幕臣・山岡鉄舟は、果たして酒には強かったのか
【15】ワイン、日本酒、そしてお茶。それぞれの魅力、それぞれの旅路。
【16】北の大地「北加伊道」に想いを馳せて
【17】高貴なるワインだけを愉しみたいなら、洞窟のご用意を
【18】楽しむことが大事なれど、楽しみ方は人それぞれに。
【19】よいワインが育つゆりかご、「蔵」について
Recent Newsトピックス
 2025年7月1日
ハンティングワールド初のハードスーツケース「シリウス」登場|美意識と機能を極めたエグゼクティブ仕様
PR
2025年7月1日
ハンティングワールド初のハードスーツケース「シリウス」登場|美意識と機能を極めたエグゼクティブ仕様
PR
冒険家が開発したフィールドバッグから歴史の幕を開けた米国発の『ハンティングワールド』。サファリツアーの経験をもとに3層構造のオリジナル素材…
記事をもっと見る 2025年6月30日
都心不動産に500万円から投資可能!アズ企画設計の小口化商品「アウラゾーナ南青山」第1号案件始動
PR
2025年6月30日
都心不動産に500万円から投資可能!アズ企画設計の小口化商品「アウラゾーナ南青山」第1号案件始動
PR
新・不動産小口化商品の第1号案件が来月より販売開始 まずは下のグラフをご覧いただきたい。 東京圏、特に都心5区の地価公示価格は、日本全国…
記事をもっと見る 2025年6月27日
USJ徒歩圏内!ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータで叶える上質ステイ
PR
2025年6月27日
USJ徒歩圏内!ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータで叶える上質ステイ
PR
関西圏を代表するテーマパーク、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、世界のトップブランドをテーマにした刺激的なエンターテイ…
記事をもっと見る 2025年6月18日
中小企業で働く すべての人とその家族に 金融業界ができること
PR
2025年6月18日
中小企業で働く すべての人とその家族に 金融業界ができること
PR
日本商工会議所が昨年発表した中小企業の人手不足に関する調査結果(※1)によると、「人手が不足している」と回答した企業は6割を超えたという。…
記事をもっと見る
Menuメニュー
Rankingランキング
-
氷にも耐えうるアウター、こだわりの”カナダグース”47493pv
-
トヨタが提案する車のサブスクリプションサービス44121pv
-
上に乗るだけで体幹づくり、ドクターエアの威力とは43595pv
Back Numberバックナンバー
2025年06月27日 発行
最近見た記事
- 最近見た記事はありません。

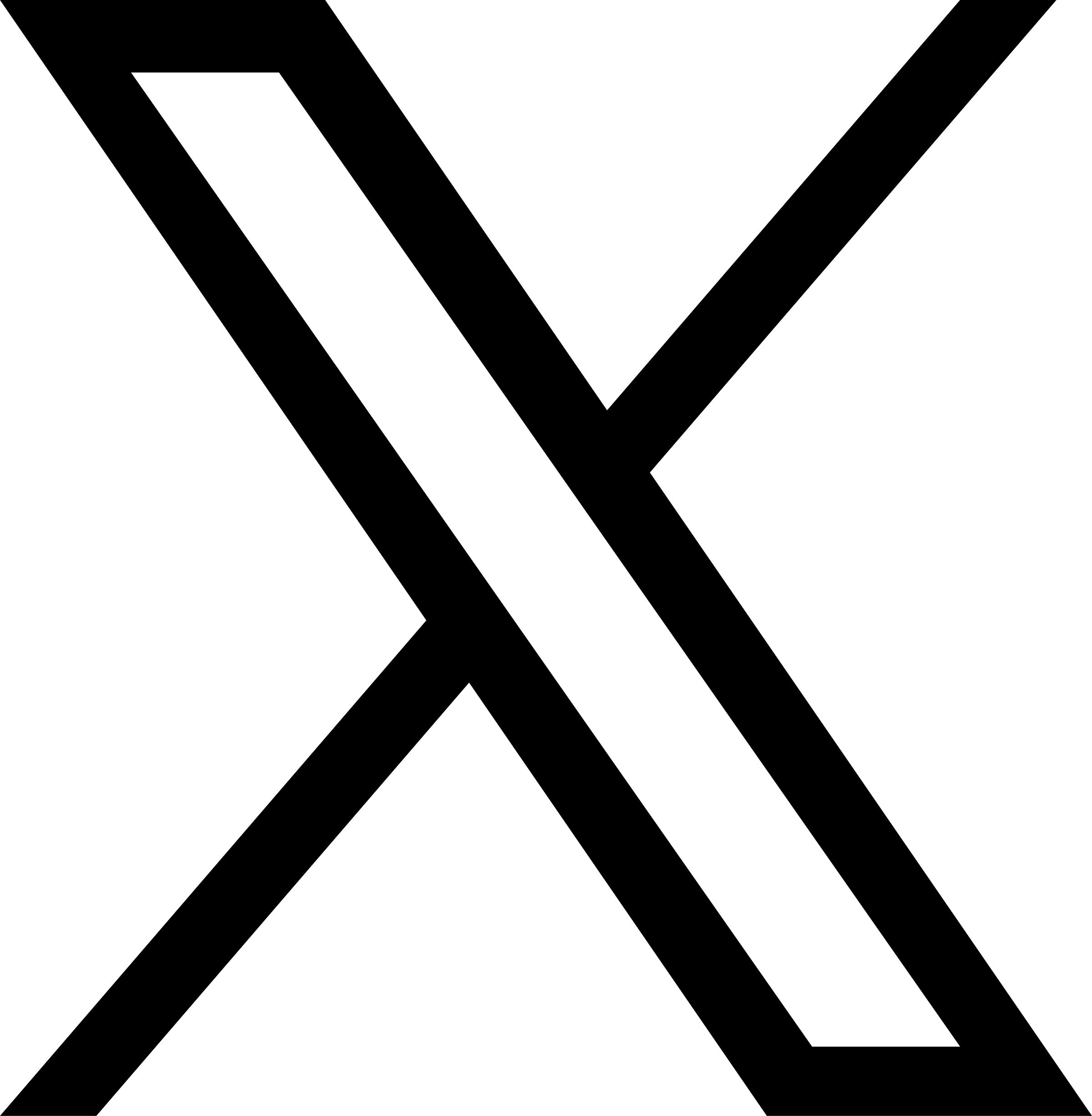

 Twitter
Twitter facebook
facebook







