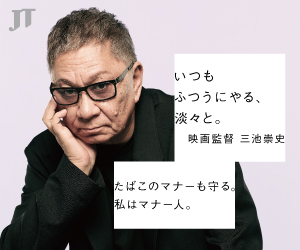- BizStyle ビズスタ東京版トップ

- Living住宅

- 家族に頼らず、自分で選ぶ。 変わり始めた、シニアの住意識

家族に頼らず、自分で選ぶ。 変わり始めた、シニアの住意識
![]() 2025年11月10日 PR
2025年11月10日 PR
介護サービスの持続性が社会的課題として浮上している。人手不足や費用負担の増大など、制度的な限界が露呈する中で、多くの人が心に抱くのは、自立した暮らしを末長く続けたいという切実な願いだ。一方的に支えを求めるのではなく、支え合う一員として社会とともに生きたい―。そんな前向きな意識が、シニア世代の風景を変えつつある。かつての「老後」といえば、子どもとの同居か、介護施設への入居が一般的だった。だが、価値観の多様化が加速するいま、状況は大きく変化。自分の力で生活を維持できるうちは自由を楽しみ、子どもや親族に負担をかけず、自分らしく生きたいという意欲が高まっている。環境を自ら選び、能動的に老後を設計する人々の姿が目立つのだ。
こうした意識の変化を背景に、2020年代に入って大きくクローズアップされているのが「自立した暮らしを支える住まい」という考え方だ。国土交通省の『住生活基本計画(全国計画)2021』でも、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けるための住環境整備が重点項目として掲げられており、これを受けた動きは民間でも進んでいる。人生100年時代を迎えた現在、介護の問題と並行して、「老後をどう過ごすか」は真剣に向き合うべき社会的テーマとなりつつある。
その象徴となっているのが、シニアの住環境の多様化だ。定番の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に加え、シニアライフに最適化しながらも自由さと安心機能、そして資産性まで兼ね備えた新しい選択肢が登場。多くのアクティブシニアが、こうした新しい住まい方に可能性を見出し始めている。そこで次ページでは、その背景と広がりを探ってみたい。
自分で選ぶ時代の到来。変わりゆく「老後の住まい」

「子に迷惑をかけたくない」世代はどんな住まい方を望んでいるのか
「老後の住まい」は、かつて家族の中で決めるものだった。病気をはじめ、体力や認知機能の衰えなどで親が思うように動けなくなると、子どもが代わりに高齢者施設を探す。核家族化が進行しつつも絆が強く、地域の支えも残っていた時代には、「終の住処」は子どもが決めるのが一般的だった。だが、人生100年時代を迎えた現在は、状況が一変。平均寿命の延伸とともに、シニアの生き方そのものが変わり始めたのだ。
とりわけ団塊世代の次の世代、戦後の豊かさとともに歩んできた70代前後からは、自らの意思で「第二の人生の住まい」を選ぶ人の姿が目立つ。背景にあるのは、経済的な安定と価値観の転換だ。高度成長期の真っ只中を駆け抜けてきた世代は、蓄えや退職金、持ち家などの資産を保有する層が厚く、「老後は自分で決めたい」「子どもに迷惑をかけたくない」という自立志向も顕著。内閣府の調査※1でも、「家族に介護の負担をかけたくない」と答える人は6割を超えており、自らの判断で「老後」そのものを設計する人の増加を裏づけている。
背景には、平均寿命よりも健康寿命を重視するヘルスケア意識の高まりもある。アクティブに動ける期間が延びれば、自分らしく過ごす時間が増えることに直結する。健康で活動的に過ごせる間は自由な毎日を楽しみ、同時に老後の基盤を確保しておきたいという考え方は、実に効率的でもある。また、最近では身の回りを整理して暮らしをスリム化する「老前整理」、あるいは元気なうちに住まいを見直す「アクティブ・リロケーション」といった考え方も浸透。つまり、安心をベースに可能な限り自立を保つことが、シニアライフの新たな常識になりつつあるわけだ。
こうした意識変化は、住み替えのタイミングを大きく早めることにもつながる。かつては80代以降、即ち介護が必要になってから施設を探すのが一般的だったが、現在は70代前半、早ければ定年直後の60代後半で具体的な行動に移す人も珍しくない。老後を「終末への準備期間」ではなく、「再出発のステージ」と捉える。こうした前向きな姿勢こそ、いまの時代を映すトレンドと言ってよいだろう。
そんな意識の裏返しか、従来型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に対しては「まだ早い」と感じる人も少なくない。自由を愛するアクティブシニアにとっては、安心と引き換えに伴う生活上の制約に、どこか窮屈さを覚えるケースも。こうした施設では、介護や見守りといったサポート体制が整う一方で、食事や外出の時間、居住空間の使い方などに一定のルールがあり、集団生活の延長線上にある側面も否めない。また、賃貸や利用権方式が主流のため、入居後に資産として残すことが難しく、費用面でも「消費型」の選択となりやすい。かと言って、一般の分譲マンションはシニアライフに欠かせない安全・医療・生活支援の体制が十分でなく、老後の不安を払拭し切れない。こうしたギャップの中から、いま新たな住まいの形として注目を集めているのが、「シニア向け分譲マンション」という選択肢だ。

老人ホームでも一般マンションでもない所有と安心を両立する新スタイル
シニア向け分譲マンションとは、自立性を重んじながらも安心して暮らせる環境を備えた、持ち家型のシニア住宅だ。管理型の入居施設とは思想が異なり、日常の自由度を大切にしつつ、必要に応じて介護や医療サービスを受けられる体制を整えている。分譲という形態自体は一般のマンションに近いが、シニア世代という明確な居住者像に合わせて設計・運営される点が大きく異なる。ブランドや物件により差異はあるが、段差のない動線や緊急通報・見守り機能、常駐スタッフの生活支援、コミュニティ形成など、加齢に伴うリスクを抑えながら自立を支える工夫が随所に盛り込まれているのがポイントだ。
最大の特徴は、部屋を購入することで専有部分の所有権を持てる点にある。入居後も資産として管理でき、相続・売却・賃貸などの選択肢を維持することが可能。この「所有権を残したまま安心を得る」という発想は、利用権や賃貸契約の老後=消費という固定観念を覆し、老後=再投資という新しいライフプランを提示している。これにより、「守る」ことのみに主眼が置かれがちだったシニアの住まいのあり方が、多様化の道を歩み始めたのだ。
表紙でも紹介したが、国土交通省の住生活基本計画でも、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせる住環境整備が重点施策に掲げられており、この流れが分譲型シニアマンション市場の拡大を後押ししている。現在は生活利便性の高い都市近郊を中心に供給が進み、駅近立地や自然環境を活かすなど個性的な物件も増加。利便性とゆとりを併せ持つハイブリッドな視点が、自分らしい選択を求める現代シニアのニーズに合致しているのだ。

所有と安心を両立させた高齢者向け分譲マンションブランド
シニア向け分譲マンションは、すでに複数のブランドが成長を続けている。中でも代表的なのが、フージャースグループが手がける『デュオセーヌ』シリーズだ。20年以上にわたり全国各地で着実に実績を積み重ねてきた草分け的な存在で、累計3307邸という供給戸数はシニア分譲マンションとしてはトップシェア※2を有する。首都圏をはじめ関西や東北など主要都市に物件を展開し、地域特性に合わせた設計思想と運営体制を築いている。
ブランドコンセプトとして掲げているのは「自分らしく輝ける、最高の舞台」。単に老後を支えるのではなく、人生を楽しむための舞台づくりを志向する姿勢は、現代のシニアのニーズそのものだ。第三者管理方式の導入により、理事会運営など煩雑な管理業務から入居者を解放し、専門スタッフが設備の保守や資産価値の維持を担う仕組みを整備。長年の経験に基づく建物の長期修繕計画や管理ノウハウも確立されており、住まう快適性と所有する価値を両立する体制が整う。

館内には365日・24時間体制でスタッフが常駐し、日常をサポート。看護資格を持つスタッフも常勤し、健康相談や協力医療機関との連携まで幅広く対応している。さらに介護事務所を併設し、居宅介護支援や訪問介護に対応する継続居住システムを導入。元気なうちは自由に外出や趣味を楽しめる環境に加え、高齢者施設を思わせるサービスも備えた住環境は、まさに「自立と安心の両立」と言えよう。
また、物件によってレストランや温泉大浴場※3、ラウンジ、ライブラリなど個性的な共用空間が多数。ホテルライクな日常を楽しめる上質な空間が整っており、居住者同士の交流を促すイベントやサークル活動も運営されるなど、自由でありながら活気に満ちた暮らしを支える工夫が随所に息づいている。住戸プランは、コンパクトな1LDKから100㎡超の2LDKまで幅広く、戸建志向のシニア層から、40〜50代の子どもが同居する二世代入居、ペット同居といった現代の多様な暮らし方に対応する。さらには断熱性能や遮音性にも十分に配慮されるなど、クオリティ志向の一般マンションに引けを取らない住性能も魅力だ。
人生100年時代を自分らしく暮らしたいシニアにとって、介護施設でも賃貸住宅でもない新しい選択肢として注目を集めるシニア向け分譲マンション。その代表格として認知を広げている『デュオセーヌ』シリーズは、所有と安心を両立し、シニアが夢見る自立した生き方を形にしてくれる。賢いシニアのポジティブな選択となりそうだ。
※1:内閣府「令和6年版 高齢社会白書」
※2:1990年以降に全国で分譲されたシニア向け分譲マンションの供給実績。株式会社タムラプランニング&オペレーティング調べ(2025年8月現在)。
※3:一部物件で天然温泉を採用。給湯方式や泉質などが異なり、大浴場のない物件もあり。
- 1
- 2
Recent Newsトピックス
Menuメニュー
Rankingランキング
-
氷にも耐えうるアウター、こだわりの”カナダグース”48233pv
-
トヨタが提案する車のサブスクリプションサービス44534pv
-
上に乗るだけで体幹づくり、ドクターエアの威力とは44303pv
Back Numberバックナンバー
2025年12月19日 発行
最近見た記事
- 最近見た記事はありません。

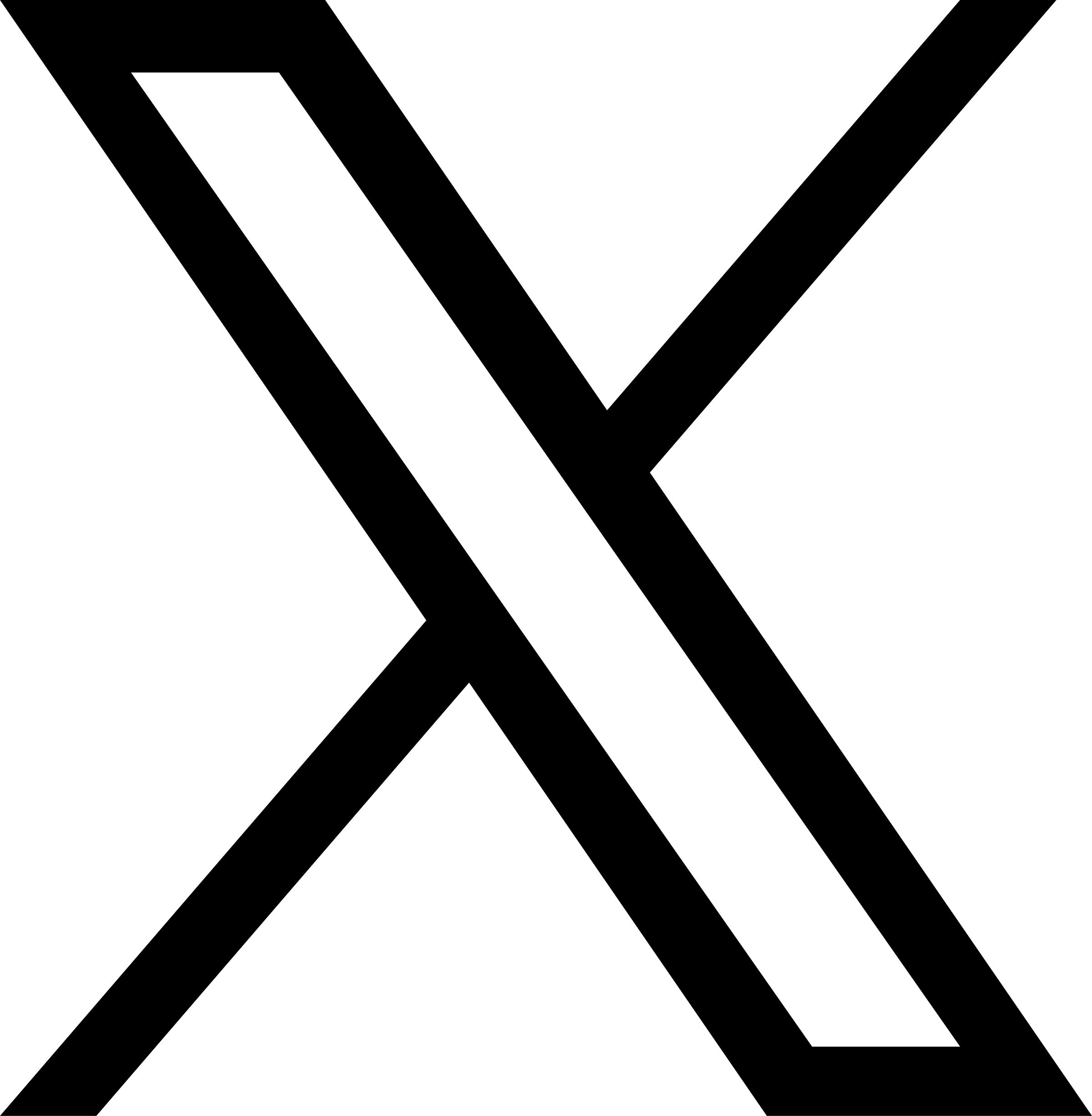

 facebook
facebook